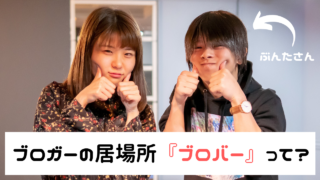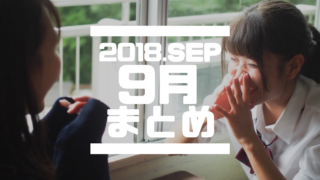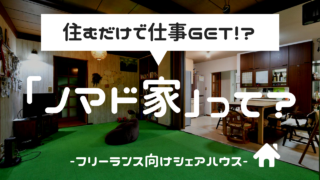にゃっほー! ゆぴ(@milkprincess17)、17歳です!
今回はずっと気になっていた『ニッポン制服百年史―女学生服がポップカルチャーになった!』に行ってきたので、感じたことを書き記しておこうかと思います。
制服に憧れを抱き、日常的に来ている身として、そのルーツや変遷を辿るのはかなり面白かったです。
『ニッポン制服百年史』の概要

開催期間:2019/04/04(木)〜2019/06/30(日)
時間帯:10:00〜17:00(最終入館16:30)
料金:一般900円 / 大学・高校生 800円 / 中・小学生 400円
会場:弥生美術館
最寄り駅:根津駅 / 東大前駅
ガングロ・チェックのミニスカート・コギャル・ルーズソックス…平成は制服の時代だった!?平成の30年間でガラパゴス的進化を遂げた日本の洋装女学生服。
百年前に日本にやってきた女学生服がコギャル文化をうみだし、「Seifuku」になるまでのクロニクル。
制服の誕生から現在に至るまでを辿る展示会。
江口寿史さん、森伸之さん、藤井みほなさん、今日マチ子さんをはじめとする、制服文化を愛するクリエイターたちによる作品の展示が話題に。
制服そのものと、制服をはじめとする若者文化に興味のある方は必見の内容となっております。ポスターとは裏腹に、かなり真面目な内容なのでご留意を。
大人数でキャッキャ行く展示会ではなく、1人ないしは2人で黙々と閲覧するスタイルが望ましいです。
個人的には中学や高校の同級生と行くと、昔話に花が咲いてとてもよろしいかと思います。
また、館内は撮影が不可能となっています。展示された制服をしっかり目に焼き付けるのです…。なお、メモなどは大丈夫だと思うので、静かに粛々とメモを取りましょう。
個人的には、2階に展示されているクリエイターたちの制服にまつわるコメントが大変エモいのでぜひメモをして何度でも見返していただきたい!
制服は、何かを制するものではなかった
私は、制服とは何かを制するものだと思っていました。
ある種校則の一貫で、学校側から指定された衣服を纏うことで、学校外でも否が応でも「組織の一員」であることを自覚せざるを得ない。
だからこそ、制服を着たままでの不良行為はそのまま学校の印象に紐づいてしまうし、そういう行為を防止するうえでのルールとしての「制服」というのが、1番役割として大きいのだと考えていました。
組織の一員であることを示すもの、結束感を促すもの、そんな感じで捉えていました。
でも実際は違った。
もともと日本における制服の意味合いは「ブランディング」だったんです。
発祥は1919年、日本初の女学校である山脇高等学校設立の際に、山脇房子さんが人を集めるべく、ブランディングの一貫としてイギリスの制服を真似てデザインをしたもの。
当時はまだ和装がメインで、洋装の人口は1%しかなかった。
しかし、着物の着心地の悪さや使われる布多さによるコストなどのマイナス面もみんな薄々と自覚していたし、いずれは洋装へと変わっていくのだろうという予感はあった。
それを促したのも制服でした。
日本人の寸胴体型にも似合うように、1番はじめの制服はワンピースにウエストマークベルトがつけられたもので、しかも驚くべきことにこちらはほとんどデザインを変えないまま、今も残っているそう。この制服が着たくて入学する人も多いのだとか。
昔に比べたら減ったかもしれないけど、今でも制服で学校を選ぶ風潮はある気がしますよね。
ちなみに当時はセーラー服が1番人気で、採用する学校が多かったそう。使う布面積が少なかったのもポイントだったらしい。
私服校の発端は「学生運動」だった!?
服装自由の学校、チラホラありますが、元はと言えば学生運動が流行ったときに高校生が服装の自由を求めて運動を起こした結果なのだそう。
しかし、ブームに乗って起こしただけなので後輩には受け継がれず、最終的になんちゃって制服を着るようになった、というこの本末転倒感。
当時は一部の問題意識の高い学生が、それこそ「制服は不自由なもの」として捉え、運動を起こし、学校側も要望を受け入れて制服を撤廃したのは良いものの、蓋をあけてみれば意外とみんな制服を着たがっていたという…(笑)。
今ある私服校はその名残。たしかにみんな、なんちゃって制服を着ている気がします。
やっぱり学生なら、制服は着たくなるよね。だって可愛いもん!
女子高生によって進化する制服
1980年代には極端に短いセーラー服と極端に長いスカートがカワイイとされ、スケバンスタイルが流行に。当時は今の逆で、スカートが長すぎると注意をされていたのだとか。
その後、安室奈美恵さんの影響でコギャルブーム到来。自ら靴下のゴムを抜きはじめたことが発端となり、ルーズソックスが流行りました。
スカートを極限まで短くして、ウエスト部分はカーディガンで隠す。バッグや携帯にはキーホルダーをジャラジャラ付けて、肌を日サロで焼き、メイクを盛る。
「他人ウケよりも自分が1番カワイイと思う自分になる」というマインドが強くてかっこいい。
その後、制服のデザインが一新され、清楚ブームが到来。正しく制服を着ることが是とされるようになります。
そして今、リュックやパーカーなど、ゆるくラクに自分らしく私服のように制服を着るのがテッパンに。
制服は女子高生によってアレンジされ、いつしか学校の枠を超えて日本のポップカルチャーになり、「いつまでも着たくなる制服」へと変容を遂げていったのです。
制服ってなんだろう?
何かを制するものではないのだとすれば、制服って何なんだろう、と思うけど、私にとっての制服は「青春の象徴」だと思っています。
中高をアメリカで過ごした身として、日本の同い年の子たちが当たり前のように纏っている制服には強烈な憧れがありました。
当時よく描いていたイラストも、大体制服の女の子だった。「制服を着たいなぁ」「制服カワイイなぁ」と思い、日本に一時帰国をした際にはなんちゃって制服を着て、友だちと遊んだりしていました。
失われた青春。これから待っている青春。「制服」というのは私にとってそんなものです。
思い出が1ミリもないからこそ、「もう制服なんて着れないよ」という感覚にならず、普通に衣服として纏えているのかもしれません。
ただ、日本で過ごしている人たちで制服を纏ったことはない人はいないと思うので、みんな「制服」に対しては何かしらの思いを抱いているし、捉え方も様々なんだろうな、と思います。
今回の展示会にクリエイターとして参加している今日マチ子さんの制服に対する考察もステキだったので置いておきます。
個性とは別に派手な服を着ることではないですよね。制服を着た姿の内側から浮かんでくるその人らしさ、それが個性ではないかと思います。
制服とは決して無個性の象徴ではなくて、むしろその人らしさであり、逃れられない個性とは何かを考えるきっかけを与えてくれるものかもしれません。
これは就活におけるスーツの話と少し通ずるものがあって、同じような服を纏っているからこそ、同一ではない個性が滲み出てしまうというか。制服を着ることで否が応でもそれと対面してしまう、という捉え方です。
だとすると、制服を自分なりに着崩してオリジナリティを出すのは何なんだろうな。
女子高生的には制服は無個性の象徴で、それを着崩すことで個性を出そうとするけど、実は本当は着崩さなくても個性はそこにあるんだよ、ということなのかな。
まとまらないけど、こんなにじっくりと制服について考えることもないので、大変興味深かったです。
気になる人はぜひいってみてください。